|
���ȉ��̕��͂̐����\�L�Ȃǂ́C�V���f�ڂ̂��̂Ƃ͎�قȂ�܂��i���L���{Web�]�ڎ��ɒlj��j
�@���������ɊS���������̂́C�w������̍u�`�ŁC�A�Z�X�����g�i�]���j�Ƃ���������̂�����ł��B���̍�肪��{�̍H�w���ŁC���ւ̔z���̕K�v����������ꂽ�̂͐V�N�Ȉ�ۂł����B�ŋ߂��O�����グ�����X�N�i�댯�j�Ƒg�ݍ��킹�����X�N�A�Z�X�����g�Ƃ����ꂪ���p������Ȃɂ��y�[�W������܂����C�e�N�m���W�[�A�Z�X�����g�i�Z�p�]���j�Ƃ����ꂪ���߂Č����ɗp����ꂽ�̂́C1966�N�̃A�����J��@�̉Ȋw�E�Z�p�E�J�����ψ���ɂ����Ăł����i��g���X�u����Ȋw�Z�p�ƒn�����w�v*1�j�B
�@�ł�������̌���Љ�Ă��ꂽ�搶�Ɋ��ӂ������C�A�Z�X�����g��@�̊m���͓���C�Ȃ��Ȃ��蒅���Ȃ������Ɏ��X�Ɗ���肪�L�����Ă��܂��Ă��邱�Ƃɂ͂��炾�����o���܂��B
�@�A�ڑ�P����Why�Ƃ�����ŁC�Ȋw�͉ߋ��̌o���̐ςݏd�˂܂��Ċ댯�������̂������ł���Əq�ׂ܂�������ǁC�V���������ɑ��Ă͖��͂ŁC���Ƃ��N��������ł������́E�]�����ł��Ȃ��ꍇ������C�����a�i��W���j�ł͂��ꂳ��������ꍇ�����邱�Ƃ������܂����B
�@�Ⴆ�C�V�������w�����ɂ��Ă͊��m�̓Ő��ł����������ł��Ȃ����*2�C���w�����ߕq�ǁi��S���j�Ȃǔ��a�̎d�g�݂���ʊW���킩���Ă��Ȃ��ꍇ�͋K���ł���@�����Ȃ����Ƃ���C�ň��̉\�����l�����Ă��̗��p�𐧌������\�h�����Ƃ����l�������K�v�ɂȂ��Ă��܂��B���̏ꍇ�َ͑���쐶�����Ȃǎ�҂ւ̔z�����������܂���B
�@DNA�̓�d�点��\���i��P���j�������Q�l�̂����C�N���b�N���m������S���Ȃ�܂���*3�B�u�q�g�Q�m���Ɛl���Ɋւ��鐢�E�錾�v�i1997�N���l�X�R����j�ɂ́C�u���l���A���̈�`�I�����̔@�����킸�A���̑����Ɛl���d����錠����L����v*4�Ƃ���������܂��B���w�����C���O���C���ː��ȂǁC�̂��ƂɈقȂ�M�d��DNA��������*5�����𑝂₷�s�ׂ́C�l�Ԃɑ��Ă���łȂ��C�������Ƌ������Ă��鑼�̐�����DNA�d����Ӗ��ł���߂Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���Y�g�L�̐�Łi��Q���j�Ȃǎ��Ԃ��̂��Ȃ����Ƃ𑱂��Ă��Ă��Ȃ���C��ł̋���̂��鐶���̈�`�q�o���N����낤�Ƃ����v�悪�C�M���X�ŏo�Ă��Ă���̂�*6�C�K�v���������锽�ʁC�{���]�|�Ƃ������Ȋw�̂�����̂悤�ȋC�����Ă��܂��܂��B
�@�J�b�g�́C�������q����́u���̊��헪�v�i��g�V���j*7�ɏo�Ă����}�̍��W�������肵�āC�����̃L�[���[�h������ɏ��������̂ł��B���ۑS�ƌo�ϊ����𗼗��������@�̕���W�����C�����P�̂��߂ɌX�l�����ԂƘJ�͂����������Ă����C�̂悤�Ȋ������厖�ɂȂ��Ă��܂��B�L�Q�������܂ނ��̂�S�~�ɂȂ���̂�Ȃ��C���邢�̓S�~���Ă��˂��ɕ��ʂ���Ȃǂł���Ƃ��납��n�߂������̂ł�*8�B
�@�i�m�e�N�m���W�[*9�ŏd�v�ȕ����̈�ł���T�b�J�[�{�[���^�̃t���[�������q*10�̖��O�̂��ƂɂȂ������z�ƁE�v�z�Ƃ̃t���[�́C���E�����ʂ���d��ȋ��ЂƂ��āC�j����E�������E�������̌��@�inuclear weapons�Cpollution�Clack of integrity�j �� �̂R�������܂����i�u���p�蒟�v1988�N7����*11�j�B���邢�͂��̂R�Ԗڂ����ő�̋��Ђ����m�ꂸ�C�����̉����ɂ������������߂����Ƃ��������Ȃ��ł��傤�B
�@���āC���̘A�ڂ�����ŏI���ł��B���w��������X�N�Ȃǖ���������o���܂������C�`���ɏ������悤�ɂP�̌��t��m���Ă�����葱���邱�Ƃ́C�����̐��E���L���邱�ƂɂȂ���ƐM���Ă��邩��ł�*12�B
�@�K���Ȃ��Ƃɍ��̓C���^�[�l�b�g���ǂ�Ȍ��t�ɂ��Ă������Ă���܂��B�{�A�ڂ͊����Ɠd�q����g�ݍ��킹�ė��p���Ă��炤�����̈�Ƃ��l���Ă��܂����B�A�ڂ͏I����Ă��C�E�F�u��ł͐V�������M�����������ł�*13�B���ǂɊ��ӂ���Ɠ����ɁC��������������������p������������肪�����v���܂��B
 *1 �����T�E�����O�Y �ҁC�u��g�u���E�n�����w�P�@����Ȋw�Z�p�ƒn�����w�v�Cp.199�C��g���X(1998)
*1 �����T�E�����O�Y �ҁC�u��g�u���E�n�����w�P�@����Ȋw�Z�p�ƒn�����w�v�Cp.199�C��g���X(1998)
*2 �������w�����ł��Ő��]�����ς�邱�Ƃ������C�Ⴆ���V�b�N�n�E�X�i��T��j�Ŏ��グ���z�����A���f�q�h�͍ŋ߂ɂȂ��Ĕ������F�肳�ꂽ�G���ۂ����@�ւ��z�����A���f�q�h�̔������ނ�ύX�i�Z�܂��̉Ȋw���Z���^�[�C2004/08/02�j�C���������F�z�����A���f�q�h��F��@WHO�i�����C2004/08/07�j�ȂǎQ��
*3 �Ⴆ�C�]��F�t�����V�X�E�N���b�N����@88�@���������m�i�����V���C2004/07/30�j�GDNA�ɂ��Ă����T�̕��qNo.19  �ȂǎQ�� �ȂǎQ��
*4 �Ⴆ��DNA���ꃖ����������ăw���O���r���^���p�N���i���q���f��  �j�̃A�~�m�_����قȂ邱�Ƃɂ�銙�`�Ԍ����ǂ́C�_�f�^���\���Ⴂ���߂ɕn���ǂɂȂ邪�ieProts���^�w���O���r��S�Q�Ɓj�C���̈���}�����A�ɂ�����ɂ����Ƃ������_�������Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B�܂��C�������̂�H�ׂĂ��A�����M�[�ɂȂ�l�ƂȂ�Ȃ��l������̂��C����X�g���X�ɑ��Ă��ׂĂ̌̂��܂����������_���[�W���Ă��܂��ẮC���̎�͈ێ��ł��Ȃ����Ƃ��炷��Γ��S�ł���ʂ�����B��`�I�ȗv���ŏd���a�ɂȂ��Ă��܂��͓̂����҂ɂƂ��Ė{���ɂ炢���Ƃł��邯��ǁC���̐l�Ԃ͈ȏ�̂��Ƃ��O���ɒu������ŏ��������K�v�����邾�낤�B�������C���̂悤�ȉȊw�I�Ȕ��z���Ȃ��Ƃ��C�����Ă���l�Ɏ��R�Ɏ���������ׂ���l����������̂�������Ȃ������ł���B��V���ŐG�ꂽ�C�g�זE����������ɂ́u������v�Ƃ������߂𑼂̍זE����邱�Ƃ��K�v�h�i�u�זE�̐����𐧌䂷��v�j�Ƃ����m���͋ɂ߂ďd�v�ł���B�����Ƃ��Ă͈ȉ��Ȃǂ��Q�l�ɂ������B �j�̃A�~�m�_����قȂ邱�Ƃɂ�銙�`�Ԍ����ǂ́C�_�f�^���\���Ⴂ���߂ɕn���ǂɂȂ邪�ieProts���^�w���O���r��S�Q�Ɓj�C���̈���}�����A�ɂ�����ɂ����Ƃ������_�������Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B�܂��C�������̂�H�ׂĂ��A�����M�[�ɂȂ�l�ƂȂ�Ȃ��l������̂��C����X�g���X�ɑ��Ă��ׂĂ̌̂��܂����������_���[�W���Ă��܂��ẮC���̎�͈ێ��ł��Ȃ����Ƃ��炷��Γ��S�ł���ʂ�����B��`�I�ȗv���ŏd���a�ɂȂ��Ă��܂��͓̂����҂ɂƂ��Ė{���ɂ炢���Ƃł��邯��ǁC���̐l�Ԃ͈ȏ�̂��Ƃ��O���ɒu������ŏ��������K�v�����邾�낤�B�������C���̂悤�ȉȊw�I�Ȕ��z���Ȃ��Ƃ��C�����Ă���l�Ɏ��R�Ɏ���������ׂ���l����������̂�������Ȃ������ł���B��V���ŐG�ꂽ�C�g�זE����������ɂ́u������v�Ƃ������߂𑼂̍זE����邱�Ƃ��K�v�h�i�u�זE�̐����𐧌䂷��v�j�Ƃ����m���͋ɂ߂ďd�v�ł���B�����Ƃ��Ă͈ȉ��Ȃǂ��Q�l�ɂ������B
�@�@�E�X�������C�u�����w�ɉ����ł��邩�v�C�������[(2001)
�@�@�E���L�ׁC�u��`�q�̏h��@��w�����w�����̕s�v�c�v�CPHP������(2004)
*5 �Ⴆ�CDNA�̐Ǝ㐫�Ƌ��x�� 
*6 ����Łu�m�A�̔��M�v�A��Ŋ�@��DNA�ۑ��� �p�@�ցi�����V���C2004/07/28�j
*7 �������q�C�u���̊��헪�v�Cp.9�C��g�V��(1994)�G�����ł͂܂������قȂ���������Ȃ���Ă���C�Ⴆ���B�́g����j�C�o�ϓI�ȑ����������s�ׂł��邩��C����͂��肦�Ȃ��h�Ƃ��邪�i���҂̏o�œ����̍l���Ƃ��āj�C�푈��e���͂܂��ɂ��͈̔͂ɓ���ł��낤�B
*8 �S�~���Ɋւ��Ă͘A�ڂł��܂�ڂ����G��Ȃ��������C���m�͍��ꂽ�ȏ�B���Y�����ʁ��̔�������̉��ꂩ�ōŌ�͔p������邱�Ƃ��܂��O���ɒu���K�v������B�Ⴆ�X�[�p�[��R���r�j�̔������܂����p�҂���������͈��̐��Y�ʂ��ێ�����Ă��̌o�H�̂ǂ����ŕK���p�������B���T�C�N���Ƃ������P�̍�ł͂Ȃ����{�I�ɉ�������ɂ́C���p�҂��啝�Ɍ����āC���Y���Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ����Ɏ��炵�߂邵���Ȃ��B�܂�C����̔������ʁ����Y�Ƃ����t�B�[�h�o�b�N�ɂ���ĕs�v�ȁi���邢�͉ߏ�ȁj���i�̐��Y�}���C���ɗ��ӂ������i�̑����Ɍ��т����邱�Ƃ����߂ĉ\�ɂȂ�i����̓J�b�g�̃L�[���[�h�gIT�ɂ��K���K�ʐ��Y�h�Ƃ��֘A�G���Y�E�p�����x���Łg���h��������Ɗ��p���邱�Ƃ́C�����̃V�X�e���Ɍ��K�����Ƃł�����j�B���̂��Ƃ��C�ƒ�E�E�ꃌ�x���C�n�惌�x���C�����x���Őςݏd�˂Ă������Ƃ����߂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��C���N�̔ߜ̂�7.13���Q�ł���ʂ̃S�~�̏��������ƂȂ������C�������10���ŐG�ꂽ�悤�ɁC�����E�G�l���M�[�������Ă��s�v�ȃ��m���̂Ă��Ȃ���V�X�e���͈ێ��ł��Ȃ��Ƃ������ł����āC�����鎖�Ԃ�z�肵�āg�p���h�Ƃ������𑍍��I�ɍl����K�v�����������Ă���Ƒ�����ׂ��ł���B���̍ہC�����Ɠ����悤�ɔp�����́g���ʁh���O���[�o�������Ă��邱�Ƃ��C�������l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�}30�@�䂪�ƂɃS�~�����Ȃ��C�V�����ɃS�~�����Ȃ��C���{�ɃS�~�����Ȃ��C�c�c
���Q�l�F�䂪���̕������x�i���ȁu����13�N�Ł@�z�����v�j
��Google�ɂ�錟����F�S�~ OR ���݁@�G���g���s�[ �b �}�e���A���t���[ �b NIMBY�i�C���[�W�����j
*9 �i�m�`���[�u�ƌ܊p�`  �Ƀi�m�e�N�m���W�[�Ɋւ��郊���N�W�f�ځG�Ȃ��C�i�m�e�N�m���W�[�ō���镨�������Ɉ��e����^����\�������O����Ă��� �� WIRED NEWS��P�i2004/01/15�j�E�Q�i2004/07/26�j�E�R�i2004/08/03�j �Ƀi�m�e�N�m���W�[�Ɋւ��郊���N�W�f�ځG�Ȃ��C�i�m�e�N�m���W�[�ō���镨�������Ɉ��e����^����\�������O����Ă��� �� WIRED NEWS��P�i2004/01/15�j�E�Q�i2004/07/26�j�E�R�i2004/08/03�j
*10 �t���[�������q 
 *11 �G�����W�w�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�@�f�U�C���T�C�G���X�v���x�Cp.25�C���p�蒟1988�N7�����G����̃��I�i���h�E�_�E���B���`�Ƃ���ꂽ�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�i1895-1983�CGoogle���������j�́C���ʑ̌��z�ŗL���ł���ق��C�n�������V�~�����[�V�������郏�[���h�E�Q�[���iWorld Game�j���l�Ă���ȂǁC�����ɂ��傫�ȊS�����B�����Ɂu�F���D�n�������c�}�j���A���v�C�u�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�̉F���w�Z�v�C�u�e�g�X�N���[���v�ȂǁB�E�̎G���\���́C�L����Dymaxion map�iGoogle�C���[�W���������C�A�j���[�V�����̂���Љ�T�C�g���j�B
*11 �G�����W�w�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�@�f�U�C���T�C�G���X�v���x�Cp.25�C���p�蒟1988�N7�����G����̃��I�i���h�E�_�E���B���`�Ƃ���ꂽ�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�i1895-1983�CGoogle���������j�́C���ʑ̌��z�ŗL���ł���ق��C�n�������V�~�����[�V�������郏�[���h�E�Q�[���iWorld Game�j���l�Ă���ȂǁC�����ɂ��傫�ȊS�����B�����Ɂu�F���D�n�������c�}�j���A���v�C�u�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�̉F���w�Z�v�C�u�e�g�X�N���[���v�ȂǁB�E�̎G���\���́C�L����Dymaxion map�iGoogle�C���[�W���������C�A�j���[�V�����̂���Љ�T�C�g���j�B
*12 ���̎��I�ȗ�Ƃ��āC��w����̐�y�ɉȊw�j�ɂ��ĕ��������Ƃ��C�O��Љ���g�Ȋw�E�Z�p�ƎЉ�h�ɊS�����悤�ɂȂ������ƂƖ��W�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���B
*13 �{�T�C�g�Ō��J���Ă���e�[�}�ʎ����E�ŐV��������蓙�Ɋւ���R���e���c���ł��Q�Ƃ��������B
|  �}�[�N�̃y�[�W�͖����̕��q���f���\���p�v���O�C��Chime���K�v�ł��i�_�E�����[�h���@�C�}�j���A���Q�Ɓj�B
�}�[�N�̃y�[�W�͖����̕��q���f���\���p�v���O�C��Chime���K�v�ł��i�_�E�����[�h���@�C�}�j���A���Q�Ɓj�B




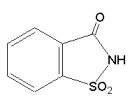













 �@
�@ �@
�@
























 *11 �G�����W�w�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�@�f�U�C���T�C�G���X�v���x�Cp.25�C���p�蒟1988�N7�����G����̃��I�i���h�E�_�E���B���`�Ƃ���ꂽ�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�i1895-1983�C
*11 �G�����W�w�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�@�f�U�C���T�C�G���X�v���x�Cp.25�C���p�蒟1988�N7�����G����̃��I�i���h�E�_�E���B���`�Ƃ���ꂽ�o�b�N�~���X�^�[�E�t���[�i1895-1983�C

