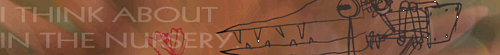
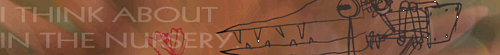
| 紳士的反骨精神 |
今回はちょっとITNとはかけ離れた内容ではあるが、一応音楽の話題。
私が好きな音楽というものは、ETCのコーナーを見ればおのずと推測出来てしまうと思うのだが、とは言えこればかりだとは限らない。もうちょっと色々なタイプの音楽を一応聴いているつもりではある。ただ、昔からダメな音楽というのも一方ではあり、意外と他人と比べて守備範囲は狭いのではないかと考えている。
例えば滅多どころか全くといっていい程聴かないというジャンルがあり、それがヘビィメタルやハードロック、ジャズといったたぐいの物。ただしヘビメタとかはそれだけでもジャンルが細分化されてしまうため一概には言えないが、メロディも無くただひたすら爆音でシャウトしまくるようなタイプの物は全くダメである。
またHIPHOPやR&Bといったタイプのジャンルは、全く聴かないとはいかないまでも、やはり圧倒的に聴かない方のジャンルである。こうしたブラックミュージック系はいくつか所有はしてるものの、好んで聴くことは少ない。ほとんどコレクターズアイテムといっていいかもしれない。
さて、問題なのが実験音楽的部類の物だ。こういったたぐいの音楽は、かつて私がオルタネイティヴミュージックやインダストリアルといった音楽を愛聴していた経緯もあって、決して興味が無い訳では無い。ましてや、それらと関連性の高い現代音楽の分野ー・・ミニマルミュージック(フィリップグラスやスティーブ・ライヒ)などを昔から聴いてきただけあって、関心がない訳ではなかった。だが、不思議な事に今まであまり首を深く突っ込んで聴いた事がなかったのである。
だが、ここ最近はこうした実験音楽のたぐいや音響と呼ばれるジャンル、そして勿論現代音楽も結構手広く聴くようになってきた。その最大の要因は実は、ちょっと金銭的な面で多少余裕が出てきて、買いたくても買う事が出来なかった物をようやく買えるようになった、というのが大きい。ダムタイプやryoji ikedaなんて、昔から関心はあったが、毎月使えるわずかなお金の配分上、ちゃんと聴きこめる無難な音楽が優先され、実験音楽のたぐいは優先順位を毎回ランク外に落とされて買うまでには至らなかった。何しろバイト稼業時代は、CDにつぎ込むお金は最大で月に2万円が限度。それでも多い方かもしれないが、聴きたい物が山ほどある中で何をチョイスするのかが毎回毎回難儀な作業だった。
と、いう訳で最近は実験音楽を積極的に買いあさっている。これは、いつまでもこんなに買う事が出来る状態がいつまでも続くとは思えない・・・という焦りもあるのかもしれない。だが、様々なタイプの音楽を聴くにあたり、ひとつ確信した事があった。
音楽は、演奏と音楽、そしてLiveこそが全てであり、それ以外の雑多な情報は実は別に無くても良いし、かえって邪魔になりかねない、と常々言われてきた。だが、私は必ずしもそうとは思わない。音楽と共にパッケージングされたジャケットアート、打ち出されているコンセプト、というのも結構重要である。
ジャケットやその他の情報が諸刃の険である事は確かだ。だったらそんな物は排除した方が良いという気持ちも解るが、意地悪な言い方をすれば、それは一種の逃げとも取れる。ジャケットやそういった物へのこだわりは、そのアーティストの志が見えてくるし、何より購入意欲をそそられる。音楽は芸術とはいえ、お店に並んだ時点でそれは商品となる。ジャケットになんらこだわりのないアーティストの作品は、他の作品と全く変わらぬ形でそこに並び、そこから独自性もこだわりも感じる事は出来なくなってしまう。故に彼らはなおのことライヴ重視になるのだ。
だが、音楽も総合芸術である。音さえ良ければいいってものではない。音楽でも、聴覚だけでなく、視覚的にも感触的にも感じれた方が面白いのだ。そしてそれを引っくるめて提示してくるアーティストが、実験音楽家の中に結構存在する。それは、彼らが音楽をやっていると言うよりはアートや実験を行っているという感覚が強く、音楽はあくまでひとつの要素であって、全てではないという考えが見え隠れしているようにも思える。実際彼らのライヴはライヴというよりもパフォーマンスといった方がしっくりするものも少なくない。映像との重ね合わせ、ダンス、空間美など様々だ。
そしてそんな実験音楽の中で特に私が気に入り、徹底した視覚的こだわりを取り入れているのが、ドイツのカースティン・ニコライが主催するRaster-notonというレーベルだ。
この人のこだわりは尋常ではない。全てがクリア系のシースルーで統一され、できる限り文字と装飾は排除されている。notonのアルバムが並ぶと、さながら透明の円盤が並んでいるような変わった光景になる。一見すると、雑多な情報を完全に排除し、音楽のみを伝えている方針のようにも思えるが、私はその全く逆だと感じる。
音楽がその空間と一体化し同化する・・・・それは言ってみれば、インテリアが空間を装飾し、一花咲かせるような感覚に似ている。音楽をインテリアのように飾るかのようなコンセプトを感じるのだ。実際、Rastar-notonが得意とする音響というジャンルは、空間との繋がりが特に重要とされている。ほとんど全てのCDシリーズのデザインコンセプトを統一しているのも、そういったこだわりがあればこそなのではなかろうか。

中でも、20分のミニアルバムを12枚組でリリースした20' to 2000シリーズは秀逸だ。2000年へのミレニアムを記念して作られたこの企画盤は、月に一枚ずつリリースされ、音響というジャンルでは著名なアーティスト達が一枚ごとに担当して話題となった。相変わらずシンプルでクリアなCD、しかもこれは中心にマグネットを入れる穴があり、12枚のアルバムが磁石で連結するようになっている変わり種であった。
これこそまさに、このレーベルらしい発想のもとの作品だった。基本的にこのCDは聴く目的以前に、CDをインテリアとしても飾れる、というコンセプトが見えるのだ。音はあくまで付随的なものだと言わんばかりに。


実際正直な話、音響というジャンルは音楽としては常に微妙、という言葉がつきまとう。私もこういったサウンドには随分慣れている方だが、それにしては未だに理解不能な所も多い。ノイズやドローン、電気的パルスといった無機的な音達が、リズムとメロディを打ち出していく。時に規則的に、時にランダムに、ある意味で数学的に並んでいる「だけ」のサウンドを、一体どこまで音楽と定義出来るのか。
しかし、ここまで秀逸なデザインを見せつけられてしまうと、そのアーティストのこだわりに打ちのめされてしまう。たとえそこにある音楽があまり理解出来なくとも、その作品の放つ美しさに魅了され、アート作品を買うような感覚で、喜んで買う事が出来る。評論家のようにあーだこーだウンチクを語る事も出来よう。でも実際の所、アートの世界は分からない事だらけだ。だからこそ面白い。例えば、その絵画から作者が何が言いたいのかなど全く分からないが、絵の放つ美しさと謎めいた不思議さに魅了されて虜になるのと一緒だ。(逆説的に言えば、音響というジャンルは理解しがたい謎な部分が多いからこそ魅力的なのだとも言える)
そのため、私はこだわりの無いやっつけ仕事のジャケットを持った音響作品にあまり興味はない。やはりそれはこういったジャンルは、音だけで全てを語る事が出来ないからなのではないかと思っているのだが。
ちなみにこの20' to 2000には興味深い事実がある。最後の月の12枚目、大トリを任されたアーティストはElphという聞き慣れないユニットなのだが、実はこれ、元サイキックTVでもあるジョン・バランスとピーター・クリストファーソンの2人からなるユニット"COIL"の変名なのである。(残念ながらジョンは04年に他界)
COILと言えば、80年代当時に活躍したオルタネイティブバンドのひとつであり、インダストリアルのジャンルを確立させた立役者達でもあった。彼らは音楽的にも世界観的にも反社会的なシュールレアリズムを継承し、常に従来の音楽スタイルから反発してきた。そんな彼らも、後年には刺々しいやり方から徐々にアンビエントなどの静かで重厚なやり方に移ってゆき、コンセプトは変わらずとも、ベテラン的大人の落ち着きぶりを見せ始めていた。
そんな彼らが最終的に音響というジャンルにまで浸透していったのは興味深い。しかし実際の所彼らの音を聴いてみると、たしかに音響作品であるが、そこにある根底的なサウンドスタイルはかつてのCOILそのものだと私は感じた。
raster-notonのような一種の美学を持った音響作品群は、一見すると、なんともアーティステックでインテリ的な部分を感じるかもしれない。だが、元COILのメンバーがそういった音を追求していったように、実は非常に社会や一般論という物に反発した音楽なのだという事も出来る。だが、かつてのCOILも、そして他のオルタナ・インダストリアル・パンクミュージシャン達も皆、非常に直接的なやり方でしかその反骨精神を打ち出す事が出来なかった。そのために皆まゆをひそめ、近づく事を拒み、社会に対する侮辱だと非難した。そして実際私もこのジャンルに嫌気がさしてしまった。
だが、raster-notonの作品を見ても、良くわからないし常軌を逸しているけど、奇麗だし、見ていて面白いと皆思うだろう。誰もそこから反発的精神を感じない。
彼らはとても地味に、そして紳士的なやり方で社会に反発しているのだ。私はこういうアプローチの仕方は大好きだし、素晴らしいと思う。デカイ声をはり上げてFU*K
YOU!!と叫ぶ事など誰でも出来る。そしてそんな連中は、彼らをインテリだと言ってさげすむ事だろう。活気がないと。熱がないと。 だが彼らも同じく熱を持っているのだ。実際は、そんな下品なアプローチでしか、自分を表現出来ない事を露呈しているのに過ぎない。そして悲しいかな、そうした方が何かと注目を浴びるのだ。音響派の中にも、暴力的なノイズを発する連中も少なくはないが、やはりそういうのは何か違うような気がするのだ。
実際の所、ずっと昔からこういった紳士的な地味なやり方で、世間の一般論と反発してきた現代音楽家は数多い。しかし、アウトローな行動を取るアーティストに我々は常に目を奪われてきてしまった。そういう反省をふまえ、今後も地味な美学を追求するアーティストを支持していきたい所存だ。