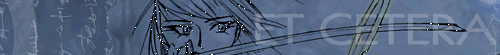
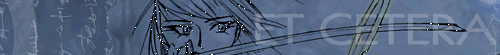
| 素晴らしきDiscreet music達 AMBIENT / CONTEMPORARY |
| Andrew Poppy / Alphabed |
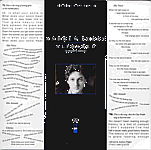 |
1. 45 is 2. Goodby Mr.G 3. The Amusement(complete version) ©ZTT records ltd. |
| 1987 Release |
ZTTレーベルといえば、あのトレヴァー・ホーンが設立し、かのアートオブノイズやフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドなど、いわゆるちょっと「お騒がせ」なアーティストを全面的に売り出して一時期話題をかっさらったレーベルでしたが、正直な所、こうした徹底的な商業的発想の売り方を押し進めていた当時のZTTのやり方に私は閉口するしか無かったですが、中には「プロパガンダ」みたいな良いアーティストも在籍していた訳で、中でもこのアンドリュー・ポピーは数あるZTTのおかかえアーティストの中でも明らかに異彩を放っていました。
この人、ZTTレーベルのコンピレーションにもしっかり混じっていたんですが、やっぱり明らかに浮いていました(爆)。だって、他のミュージシャンが当時の流行のエレ・ポップ一色なのに対し、ほとんど現代音楽的アプローチの人でしたから。だいたいなんでこんな人がZTTにいたのかが謎、っていう位、そもそも当時ZTTが押し進めていたアーティスト層と違うのですが、ま、ZTT的にはジャンルにこだわらずいいものはいいとして送り出す、という考えがあったのでしょう、しかし所詮派手で目立つアーティストに注目が集まるだけで、一向にこの人に脚光が浴びる事はありませんでした。
でも当然ながらあまのじゃく(笑)な私にとって、ZTTで最も印象に残ったのがこのポピーさんな訳で、デビューアルバムの「The
Beating of wings」の「The Object is a hungry wolf」という彼の代表曲は、もう本当に素晴らしい名曲で、キーボードメインとはいえ完全なオーケストラ演奏による現代音楽。女性コーラスが実に美しい印象深い曲です。でもこういった曲は、当時のZTTのAONやFGTHに注目していた若者達にとって、単なるクラシックにしか聞こえなかったんだろうなあ。
このBeating of wings、基本がこうした現代音楽でも、B面の「Listening in」とかはもうちょっと実験的要素が強くなって、ある種ZTT的? な趣向が強く、これもポピーさんの特徴でした。
ですが、この「Alphabed」はそうした実験要素がさらに影を潜め、全体を通して聞きやすくなった1枚で凄く気に入っています。しかし、ここまで個性的で聞きやすく、素晴らしい楽曲を残していても、陽の当たらない人には一向に当たる事が無いのも事実で、この後さらに一枚アルバムを発表したようですが、ほとんど過去の人になった状態で残念。やはりこうしたミュージシャンはなにか大きく知られるキッカケでもない限り、永久に影に埋もれてしまいますね。だいたい全部廃盤だし・・・。
ZTTレーベルは現在、過去の作品のリイシューに積極的なようなので、ポピーさんのアルバムも是非お願いしますよー。
| Brian Eno / Discreet music |
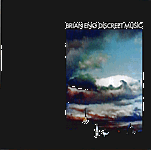 |
1. Discreet Music 2. Three Variations On The Canonin D Major By Johann Pachelbel (I) Fullness Of Wind (II) French Catalogues (III) Brutal Ardour ©EG records ltd |
| 1975 Release |
そしてこの人ですよ。イーノはもう押しも押されぬ現代音楽の巨匠ですが、学生の頃はまだイーノの事を良く知らなくて、どんなもんなんだろう?とほぼ無作為に選んで最初に買ったのがこの「Discreet
music」だったんですが、最初にこれを選ぶとは、私も勘がいいというか、よりによってこれをチョイスするとはね。当時は気にも止めませんでしたが、だってタイトルが「目立たない音楽」ですよ? もうストレート過ぎますって(笑)。
シンセっぽい音源のメロディがひたすらエコーのように幾重にも重なり、延々それがランダムに30分も繰り返されるという、アンビエント・ミュージックの元祖とも言えるこの作品、ライナーノーツにはイーノがこの作品を生み出すキッカケとなったエピソードが綴られています。
事故に遭って身動きも満足に出来ない状態の時、見舞いで友人からもらったレコードをなんとか必死の想いでプレーヤーにかけたまでは良かったのですが、音量があまりに小さすぎて良く聞こえなかったとか。直す気力もなかったのでそのまま聞きつづけたらしいのですが、この時に、音楽として一応聞けるけど、一方で無視も出来る音楽、というアイデアを思いついたそうで、それでこのアルバムが生まれたんですね。
ライナーにはさらに「出来る限り音量を絞って聞いてほしい」というイーノの言葉が添えてあり、とにかく環境音楽としてのサウンドを徹底して構築したという事が伺えます。
こういう実験的な環境音楽はよもすると地味以前に退屈、という言葉がよぎるものですが、そこはイーノの手腕の良さ、決して退屈とは言えない内容だと個人的には思っています。
繰り返されるメロディ自体が浮遊感のある美しいものですし、非常に幻想的な世界に仕上がっているからです。もちろんこのようなタイプの作品で色々と想像力が次々と溢れ出てくるとまではいきませんけど、イーノが言っているように、片手間に聞ける音楽、それでいてちゃんと退屈せずに聞ける音楽、というのはまさに私にピッタリなサウンドだと思っています。
一方でジョン・ケージのような不確定性を持った実験音楽とかは、音の芸術作品としては非常に興味深いのですが、いかんせん「音楽」とはちょっと違いますからね。やっぱりちゃんとメロディって物がなければ、聞き流す以前に雑音と化してしまいます。
ボーッと窓から見える風景を見ながらこのアルバムを聞くと、なんかとってもいいですよ。
| William basinski / Disintegration loops I - IV |
 |
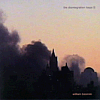  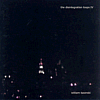 |
I 1. dlp 1.1 2. dlp 2.1 III 1. dlp 4 2. dlp 5 ©2062 |
II 1. dlp 2.2 2. dlp 3 IV 1. dlp 6 2. dlp 1.2 3. dlp 1.3 |
| 2001 Release |
ドイツの音響レーベルの老舗にRaster-notonというのがあります。このレーベル、音響という事もあって無機質で冷たく、音楽と呼ぶのには少々はばかる、といった感じのノイズ系サウンドが大半を占めているんですが、そんな無機質・無味乾燥なサウンドの中にあって数少ない叙情派というか、美しいサウンドを聞かせてくれる希な存在のアーティストが所属しています。それが今回紹介するWilliam basinskiです。
まあ美しい、叙情派とはいってもあくまでこのレーベルの中で比べての事であって、世間一般的尺度で言うと相当にマニアックな部類の音楽をやっている人です。
ラジオノイズを巧みにサンプルループとして利用したり、延々引き伸ばされたテープループによる楽曲がこの人の特徴で、そのなだらかなサウンドテクスチャはブライアン・イーノ辺りの影響を色濃く感じる物です。
そんな彼の入魂の一作、自身の2062レーベルからリリースされたCD4枚にも及ぶ「Disintegration
loops」シリーズは、イーノを思わせる美しいサウンドループがそのタイトル通り、徐々に崩壊していって聞こえなくなっていく様子を延々収録した実験作品です。
この作品自体は彼がずっと昔に作っていた音源で、それをCDに再収録しようと編集をしていたところ、さすがに音源が古かったせいもあるのかテープが徐々に傷んで音が歪んでいってしまったらしく、最後には再生不能な状態にまでなってしまったそうです。普通の人だったらこりゃもう使えん、とあきらめる所をこの人はそのアクシデントをそのまま作品の一部として発表してしまったのです。転んでもタダでは起きぬというか常人には考えつかない所業です。
しかもこの制作をしている時に例の911事件が起こり、自宅の窓からモクモクと黒煙が上がっているのを目の当たりにしてしまった彼は、運命的な物を感じたのか、作品を急遽この911事件に捧げる事にしました。彼は固定カメラを設置してその事件の様子を延々撮影していたそうです。ジャケットはそのワンシーンからとられたものですが、この映像は最近DVD化されてリリースもされています。
一見するとなんとも不謹慎にも思える行為と感じるかもしれません。しかし目の前でそんな事態が起きてしまった以上、アーティストとして何かしなければならない、という強迫観念にも似た気持ちにかられたのではないでしょうか。徐々に崩壊していく音楽と、目の前で崩壊していく日常。そんな偶然を叩きつけられて何もしない方がおかしいってもんです。もちろん彼がこれを単なる芸術的遊びの一環としてやったというような、短絡的発想で行った訳ではないことは言わずもがな、です。 事件の様子を固定カメラで延々撮っていたなんて事を考えるとつい、アンディ・ウォーホールの映像作品「エンパイア」を連想してしまいますが、ウォーホールのように死を軽視しているかのような行為では無いと思います。
(「エンパイア」はエンパイアステートビルを延々数時間も固定カメラで撮っただけという実験映画。ウォーホールは死をテーマにした作品を幾つか残しているが、どれも短絡的な感は否めない)
この作品、短い旋律が延々30分とか60分とか繰りかえされる非常にシンプルなアンビエントミュージックなんですが、前述したように徐々に聞こえにくくなって、しまいには「電池切れ?」みたいな感じの飛び飛び音になり、最終的にはもはや原形をとどめないほど崩壊して無音に近づいていきます。ちなみにこれはあくまでアクシデントなので、曲によってはほとんど崩壊しないものや、最初から音が歪んでいるものもあったりします。
音源自体がはかなくも美しいサウンドなので、それが徐々に崩壊していく様はとても悲しくもあり、美しくもあります。それは肯定も否定もせず、ただただこの事件を冷静に見つめ、聞き手に何かを深く考えるようにと訴えかけているようでもあります。
このシリーズのメインテーマとも言える一枚目のdlp1.1や、3枚目のdlp4とかは中でも特に美しいサウンドでお気に入りなんですけど、まあ一部では「寝るときに最適」とか言われてもいるみたいで、たしかに万人に薦められるようなタイプのサウンドでは無いですね。本当に同じことの繰り返しですし、古い音源のせいもあってアナログ的でモコモコしたサウンドですし。でも片手間に聴くにはとてもいい作品だと思いますよ。逆に言えば片手間に聴くにはあまりにも美しすぎ、はかなすぎるかもしれませんが。
現在、このサイトで「Disintegration loops」を映像付きで丸々クイックムービーとして見ることが出来ます。これはリリースされたDVDと物は同じです。音楽同様、これもまた延々黒煙がモクモクと上がっているだけの映像なんですが、もう何も語るまいというか複雑な気持ちにさせられる映像です。
なおこういった複雑な事情を抜きにしても音楽自体は大変素晴らしい物だと思うので、普段マトモな音楽しか聴いてない初心者の方々も、たまにはこういう実験音楽にトライしてみるのも一興なのではないでしょうか。 その入門としてBasinskiの音楽は最適といえるでしょう。DVDリリースで再入荷されつつあるので今なら手に入りやすいかも? とは言え私自身は、これ以上深い所にはさすがについていけないんですけど・・・・。やっぱりこの辺が限度(笑)
| Johann Johannsson / Viroulegu Forsetar |
 |
1. Part1 2. Part2 3. Part3 4. Part4 ©Touch |
| 2004 Release |
実際にはOの文字の上に濁点とか入るんですが、とするとヨーロッパのどこかの国か、と調べてみたらアイスランドの御方。イギリスの音響レーベルの名門TOUCHからリリースされた、今回がセカンドとなるアルバム。
この人は元々実験音楽家というよりは、舞台やTVのサントラ制作など多岐に渡る音楽活動を行っている人で、ファーストアルバムではそうした舞台のための音楽などを集めてコンパイルした作品集だった訳ですが、今回は60分間による組曲構成のまさにアンビエントのお手本のような楽曲。一応4パートに別れてはいるものの、基本的に曲の流れはずっと一緒。オルガンやブラスなどのクラシック楽器をメインにしたメロディが基本として流れるのですが、盛り上がったかと思うと、ブーンという低い電子音(ほとんど無音といっていいかも)で静寂が続き、ん?と思っていると再び盛り上がってメロディが流れ、再び静寂、というこの繰り返し。特に中盤になると無音部分がヤケに長くなり、アレ?と我にかえる事も。
この音楽は元々教会という一風変わった場所にて演奏されたライブを元に再レコーディングされたもの。勿論同じ場所を使って録音したようですが、実際のライブはもっと長時間にわたるものだったようです。教会という独特な場所における音の残響や空間の雰囲気が非常に重要だったため、本来はライブでないと意図した物が伝わらないようですが、そこで今回はわざわざ5.1チャンネルのDVD-AUDIO版が付いているんですね。実際DVD版の方が電子音パートの微妙な音の変化がはっきり聞こえます。
実験音楽として片づけられてしまいそうな内容ですが、不思議な曲構成だとかなんとか以前に、とにかくメインのメロディが美しすぎです。ブラスバンドによる静かで力強い演奏が耳に残ります。合間合間にしか流れないからこそ、かえってそこの部分が際だって聞こえ、同じようで実は演奏もカラーがあって全く同じではないため、意外と飽きが来ません。
こういう音楽を聴くと、いつも自然に流れている「時間」をスポットに当てて表現しているようで、例えば徐々に景色が移り変わっていく日の出や、しんしんと降り積もる雪景色といった、ずっと同じ景色のようで実は目まぐるしく変化しているというような空間。静寂の中の嵐とでもいいますか、見た目全く無機質なんですが、実は内面に物凄い躍動感が隠れているとかそういうような・・・・。うーん文章では表現しずらいな。
このアルバムの意図はどうあれ、アンビエントミュージックの真骨頂ともいえる「ながら」音楽という点では充分に役目を果たしてくれる音楽です。実際、仕事中に何を聴きながらやろうかという時に、迷ったらいつもこれを引っ張り出してましたね。メロディも美しいし、アンビエント系では久々のヒットです。でもこれをライヴで聴いていたら、多分途中で寝てしまうかも(爆) やっぱり集中して聴くタイプの音楽とはちょっと違うと思います。 一ヶ所にとどまってじっと聴くより、場所を移動しながら移り変わる風景を横目に聴くほうが実はこういう音楽に合っているんじゃないかって思う事もあります。
| James Newton Howard / Unbreakable - original soundtrack |
映画「シックス・センス」が大ヒットし、一躍注目を浴びるようになったM・ナイト・シャマラン監督。期待が高まる中、満を持して上映された彼の2作目「アンブレイカブル」。ところが評価は真っ二つに分かれ、駄作とけなす人もいれば、傑作と誉め称える人も。さすがに前作のインパクトが強かっただけに、まあ致し方ない現象ではありますが、それにしても駄作って言わなくてもなあ。私はこの映画は凄く好きです。いや、正直シックス・センスより好きかも。
普通なら派手な演出で描くであろうファンタジックな内容をテーマにしたこの映画は、あくまで非常にリアルスティックな演出法で見せ、ひたすら淡々と主人公の苦悩、決断に至るまでを描いています。特にラスト一歩手前の子供との朝食のシーンは実に素晴らしく、非常に地味ながら感動を与えてくれます。それを思うとあの衝撃的なラストはインパクトは多少低めで、オマケっぽく感じますが、それでもこの映画の本質を突いているので恐らくあれで良いのでしょう。
それにしてもみんなシックスセンスみたいな話を期待してしまったのが不幸。当時のCMも全く内容を捉え違いしてます。実際はそんな話じゃ全然無かったので。なので先入観がなければかなり楽しめると思うんですが。
で、このサントラを担当したJames Newton Howard。サントラのコンポーザーとしてはかなり売れっ子な方で、かなりの数の映画のスコアを書いているみたいです。シックスセンス以来、ずっとシャマラン監督の映画と共にある人ですが、なるべく前に出さずに、控えめに努める、というポリシーがあるみたいで、つまるところ、とにかく地味。たしかにシックス・センスとかは、音楽の旋律は全然印象に残らなかったんですよ。要するにサントラを聴いたとしてもいまいち楽しめない。映画から切り離されたサントラだけを聴いても退屈、というタイプの代表といってもいいのかもしれません。
ところが、そのハワードさんにして、このアンブレイカブルのサントラはなんなんでしょう。彼にしてはあまりにも印象に残るフレーズと自己主張したメロディ。メインテーマなんて、まるでenigmaみたいなハウスビートがオーケストラの旋律と重なり、美しさと躍動感が際立ち、ハッとさせられるほどの名曲に仕上がっています。勿論、彼にしては、という事であって地味には違いないでしょう。でも、主人公の悩める気持ちを表わすかのような哀愁漂うメインの旋律のメロディは、映画を非常に盛り立てていると思います。
映画では、主人公が悩む気持ちをふっ切ってある行動を起こし始めるのですが、そういった盛り上がっているときでもあの悲しみに満ちた哀愁のメロディが壮大なオーケストラで流れるのです。そうなると凄く励ますようなサウンドに聞こえるのが不思議ですね。このアンブレイカブルのスコアってそういう意味で絶妙だと思います。
悲しみと哀愁=励ましと勇気 という図式になっているこのサントラって、ITNの曲の感じと似ているのかもしれません。だから好きなのかな。
| Brian McBride /When Detail Lost Its Freedom |
Krankyレーベルから作品を出している「Stars of the lid」はアンビエント・ドローンを得意とするグループで、延々と長い幽玄なドローンサウンドが特徴です。個人的にこういったドローンサウンドは嫌いじゃないんですが、ちょい変化に乏しい感もなきにしもあらず。まあミニマルやアンビエントもそう変化がある音楽では無い訳だけれども、一定のフレーズが延々引き伸ばされたように弾き続けられるのを聞くのは飽きが早いって事なのか?
Brian McbrideはStars of the lidのメンバーであり、同レーベルから今回紹介しているアルバムをリリースしました。いわばソロ名義の作品ですね。さすがStars
of the lidに関っている人だけあって、その雰囲気、特徴はStars of the lidに酷似していますが、ドローン的展開というよりも純粋なアンビエント作品に仕上がっており、シンセやストリングス、あるいはギターからピアノまで様々な楽器で奏でられた本作品はボーカル物もあるなど、ある種バラエティに富んだ内容と言えなくもありません。 私がStars
of the lidを聞いた時に感じた「変化に乏しい」という感覚はかなり抑えられている印象です。
何が大きく違うのかと考えて見たところ、やはりメロディが大きく前に出ているか否かがポイントなのだろうと思われます。それぞれの楽曲に印象深いメロディが色濃く出ており、全体的に非常に静かで幽玄な世界観なのにも関らず、聴きやすくて心地良いのは恐らくそういった事が要因になっているからなんでしょう。
ブライアン・イーノのアンビエント作品がなぜ傑作と誉め称えられているかと言えば、やっぱりそれは心地よいメロディがあればこそなのだと思うし、それが皆無とあっては実験音楽の枠に留まってしまう。実験音楽は嫌いじゃないけど、音楽は心地よいならその方がいい。 brian本人は、自分の癒しのためにこの作品を作ったそうですが、なるほどならばこのアルバムの方向性も納得。癒しという言葉に拒絶反応を示す人も少なくないけど、人間が音楽に求めている物ってそこに集約されてないですかね、結局のところ。
ちなみにこのKrankyレーベルは色んなタイプのアーティストが所属していますが、中でもアンビエント・ドローン系に強いですよね。個人的にはLoscilのアンビエント・テクノ作品群や、Christopher Bissonetteのドローン・アンビエント等がお気に入りです。あと限界に近いくらいに薄っぺらなKranky特有の紙ジャケもデザイン的に好き。Plopレーベルのジャケに近いですが、あれよりも薄い。CDジャケとしては最も理想に近い形のひとつか?
まあCDスリーブを入れないと傷付きそうで怖いですけどね。
| Liam Singer / Our Secret Lies Beneath The Creek |
このアルバム、はたしてポップミュージックのカテゴリに入れるべきか、それとも現代音楽のジャンルに納めるべきか、非常に悩みました。正直どちらにも足を突っ込んでますからね。まあ便宜的にここに納めましたが。
Liam Singerはピアノをメインとした楽曲が主で、ボーカルもこなしています。隠し味的にテルミンなどを用いていますが、基本は非常にシンプルで美しいサウンドです。
彼のデビューアルバム「The Empty Heart of the Chameleon」はこの言葉通りの非常にシンプルなアルバムで、美しい事は美しいのですが、あまりにあっさりし過ぎているためかいまひとつピンと来ない内容でした。まあピアノ弾き語りによる楽曲なんてのはそんなに真新しくもないですからね。
さてセカンドアルバムであるこの「Our Secret Lies Beneath The Creek」は、彼の中で何かがふっ切れたのでしょうか、自身が影響を受けたと思われる音楽スタイルを躊躇なくサウンドに盛り込んでいます。つまり、彼がフィバイリットしているフィリップグラスやライヒといったミニマリストの音楽方法論を大胆に取り入れ、ポスト・ミニマリスト的な内容になっているのです。しかし相変わらず彼のポップミュージック的部分は残っているため、そういったポップな部分と現代音楽的ミニマルサウンドが見事に融合し、前作と比べてずっと豊かなアルバムになったかと思います。
インスト曲も多いですが、楽器もバラエティに富んでいますし、メロディセンスは良いと思うのでこれは地味ながらとても良いアルバムです。それだけでなく、今後がとても楽しみなアーティストとも言えますね。何しろまだ20代の若者ですから。
今回のアルバムは良い内容ですが、厳しい言い方をすれば、グラス等のサウンドのまんまコピーみたいな部分もあるので、そういった模倣から一歩抜き出れば、ずっと飛躍出来るでしょう。こういうポップミュージックはあんまりないので是非頑張って欲しい所です。
でもあまりに地味な活動のせいか、売ってるところが少ないのが困りましたね。レーベルサイトならまだ購入可能なようですが、超マイナーレーベルなので欲しい方は急いだ方が良さそうです。
ここで試聴も出来ますのでお試しを。