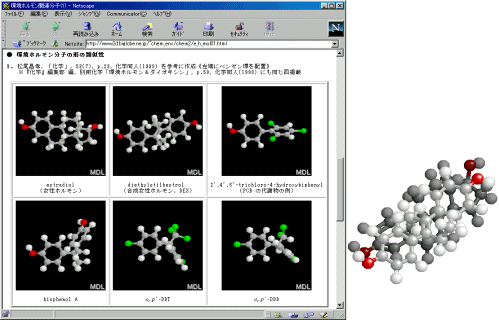
図1Webページ『環境ホルモン情報』4)で参照できる環境ホルモン関連化合物分子の例.左はブラウザでの表示例,右は分子の画像を利用した女性ホルモンの17β-estradiolと合成ホルモンのdiethylstilbestrol(色の濃い分子)の重ね合わせ画像例(文献5)を参考にして作成した模式図).
〒950-8680 新潟県新潟市海老ヶ瀬471 県立新潟女子短期大学生活科学科
e-mail: honma@muf.biglobe.ne.jp
1.はじめに
内分泌撹乱化学物質(以下,環境ホルモン)の問題が世界的に注目を浴びる中,現在はおよそ70化合物が疑わしいとしてリストアップされている。そのうちのいくつかについて環境中や野生生物・人体中の濃度測定が進められる一方,生物発生過程などにおける内分泌撹乱作用の実態について調査・研究が続けられるなど,広範な分野で取り組みがなされている。極めて低濃度での影響が懸念されることから,現在疑われている化合物だけでなく今後多数の化合物の中からスクリーニングされてくるであろう化合物についても,その微量分析技術や影響評価の手法に関する研究も必要になっていくと考えられる。
環境ホルモン問題では,その化学的な側面だけでなく,地球規模で起こっている多くの生物が直面している絶滅などの危機的状況とその考え得る原因とに関する研究情報を集めることによって見出されたのが発端であったこと,またその後の問題の周知にあたってもインターネット上での専門家以外の人々によってなされた情報提供,さらには最近になって公的機関でも資料を積極的に公開するに至る1)など,情報化時代における象徴的なできごととしても興味深い側面を持っている。
また,化学物質過敏症などとも考え合わせ,個々人の生活のあり方を含めて社会全体で人工化学物質とのつき合い方を考え直していく必要性が指摘されており,環境教育や正しい情報の提供の重要性も視野に入れていく必要があろう。
筆者が公開している化学教育と環境情報の流通を主目的にしたインターネット上のホームページ2)において,環境ホルモン問題をトピックとして取り上げて以来,その反響の大きさに呼応するために,随時最新情報を追加したり画像などを用いた資料を掲載するなどしている3)。ここでは現在作成中の資料を含めその経緯の一端を紹介したい。
2.環境ホルモン情報流通の一端
Web上における環境ホルモン問題関連情報は,当初の個人・団体レベルでの情報発信に続き,国内でも複数の省庁・公的機関などもそれぞれの担当領域に関するデータや資料の積極的な公開を推進しつつある。
筆者は1997年6月に自作ページで環境ホルモン問題を取り上げ,以後『環境ホルモン情報』としてページを独立させ4),現在に至っている。そこではインターネット情報や徐々に出版されるようになった書籍や文献情報などを適宜取り上げ,様々な画像やリンクなどを駆使して,利用者が問題の本質を正しく理解できる助けになるよう工夫している。例えば,分子モデルを立体的に表示しパソコン上で自由に動かして見ることのできる分子表示ソフトのChemscapeChime(MDL社)を利用して2),環境ホルモン関連化合物の分子モデルを参照できるようにし,構造上の共通性が少ないとされる当該化合物群を比較できるようにしている。図1はその画面例である。
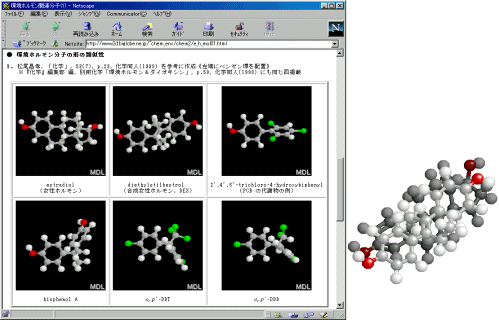
図1
Webページ『環境ホルモン情報』4)で参照できる環境ホルモン関連化合物分子の例.左はブラウザでの表示例,右は分子の画像を利用した女性ホルモンの17β-estradiolと合成ホルモンのdiethylstilbestrol(色の濃い分子)の重ね合わせ画像例(文献5)を参考にして作成した模式図).
多数の化合物の中から環境ホルモンとして作用しそうな化合物を選び出していくために様々な試験法が考案されているが,近年発達してきている計算化学の手法を援用しようとする試みがあり,例えば小林茂樹らにより化合物の生物活性と化学的ハードネスとの関係の解析6)が報告されるなどしている。
また,厚生省の『内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書』7)でも"人への簡易な毒性影響の判断を行う有力な手法"として定量的構造活性相関(QSAR)研究を上げている。
QSARの主因子は,オクタノール/水分配係数P 8)であり,化合物の親水性・疎水性の程度を示すものであるが,筆者はこれまでに化合物の性質の概略を極めて簡便に知ることのできる有機概念図9)を用いて,有機概念図の有機性・無機性値とlog P との関係を調べてきており,環境ホルモン関連化合物についても計算を行っているところである。図2・3にその一例を示す10)。
図2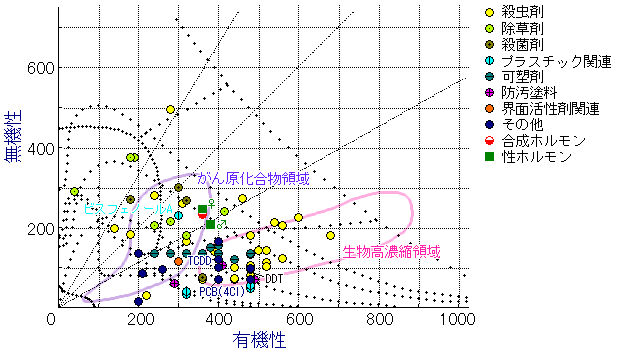
図3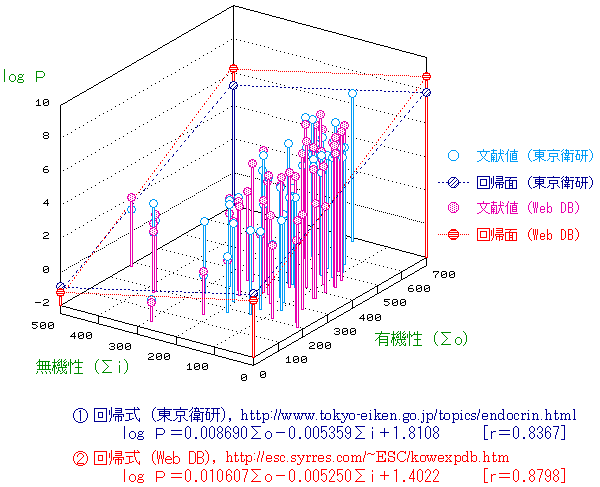
文献
1) 例えば,厚生省,『厚生科学研究「母乳中のダイオキシン類に関する調査」結果概要』,1999/08/02(Web掲載は 1999/08/17,http://www.mhw.go.jp/houdou/1108/h0802-1_18.html)
2) 本間善夫・田中直子,化学ソフトウェア学会'97研究討論会講演要旨集,p.205(1997)
3) その一部は以下で紹介;本間善夫,『インターネットにおける環境情報の流通 −"環境ホルモン"問題を例に−』,サイエンスネット,第5号,p.13,数研出版(1999)
4) 本間善夫,『環境ホルモン情報』,http://www2d.biglobe.ne.jp/~chem_env/env/eh_home.html
5) 山川浩司ほか,「メディシナルケミストリー 第4版」,p.19,講談社サイエンティフィク(1998)
6) 以下でわかりやすく解説されている,吉村忠与志,『環境ホルモンの毒性をどのように発見するか』,化学とソフトウェア,21(1),11(1999)
7) 厚生省,1998年11月,http://www.mhw.go.jp/shingi/s9811/s1119-2_13.html
8) 例えば,日本環境協会 編,「化学物質の物理化学性状測定法」,p.23,産業図書(1989)
9) 例えば,甲田善生,「有機概念図 ―基礎と応用―」,三共出版(1984)【絶版】
10) 図2・3のデータ計算と作図は自作プログラムによる;本間善夫,J.Chem.Software,4(1),p.11(1997);化学ソフトウェア学会登録ソフトウェア 9505