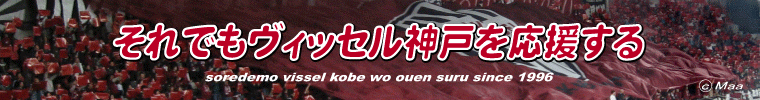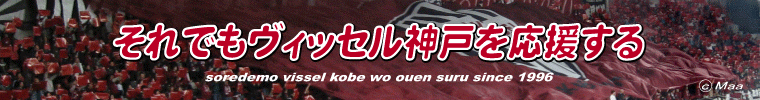|
■泣いたゴールベスト3
【その1】
J1・J2入れ替え戦 第2戦 アビスパ福岡戦 近藤 (12月9日)
いやー。これはなんと言っても今期のヴィッセル神戸を代表するゴールだった。
シーズンの終盤なかなか勝てず、優勝どころか、入れ替え戦出場となってしまい、迎えた適地福岡での第2戦。
アウェイゴール方式とルールだったので、第1戦にホームで失点しなかったのが大きかった。
第2戦で勝てば、勝ったチームがJ1行き。 0−0なら延長戦、1ー1ならアウェイで得点した神戸のJ1行き、ということになる。
そこでの先制点だ。
アツからのセンタリングを相手DFがヘッドでクリア。落ちてきたボールをボレーでキーパー足元に強烈に蹴りこんだものだった。
これで、福岡はJ1に残るためには2点取らなければならない状況になった。
このあと、福岡は猛烈な追い上げを見せるが、本当に強烈な近藤の1撃だった。
そのとき、ワタシはテレビの前で泣いた。
【その2】
第36節 東京ヴェルディ1969戦 田中 (8月27日)
ヴィッセル神戸の底力を見せつけたゴールだった。
バクスター監督が帰国する最終のホームの試合。
1点負けていて、前半終了間際に丹羽が退場となり、一人少ない状況での戦いだった。
このピンチに後半9分に河本が同点弾。
そして一人少ないながらも押していたゲームに終止符を打ったのが田中の一撃。 後半ロスタイムでの出来事だった。
朴のシュートのこぼれ球をボレーで田中が入れたもので、その瞬間、神戸ユニバーは優勝したような大騒ぎだった。
これで、神戸は大丈夫。絶対J1に行ける。絶対優勝できる。と思ったものだ。
(全然楽ではなかったが)
そのとき、ワタシはユニバーのバック自由席で泣いた。
【その3】
第51節 湘南ベルマーレ戦 田中 (11月26日)
リーグ終盤、J1復帰のためには絶対勝たなければならないという大事な試合(終盤はどの試合もそうだったが・・・)
二人の退場者を出し、後半89分まで1−1の同点という状況。引き分けではだめ、勝たなければだめという試合だ。
その逆境の中で後半ロスタイムに田中が逆転ゴールが生まれた!。
絶対に勝つ、絶対にJ1復帰、という強い気持ちが感じられた執念のゴールだった。
そのとき、ワタシはウイングのバック自由席で泣いた。
しかし、その30秒後に湘南に返されて、結局引き分けになってしまった。
そのとき、ワタシはウイングのバック自由席でまた泣いた。
このページのトップへ戻る
■悔しかった試合ベスト3
【その1】
第51節 湘南ベルマーレ戦 (11月26日)
勝ちたかったなあ。
あと、30秒我慢できたら勝利だったのに、それが我慢できない。
二人の退場者が効いたなあ。最後の相手の攻撃に全然対応できてなかったもんなあ。
勝てる試合だっただけに辛かった。
そのとき、ワタシはウイングのバック自由席で泣いた。
【その2】
第39節 湘南ベルマーレ戦 (9月13日)
審判に泣かされた。
こんな判定は今後のサッカーのためにあってはならない、と思った試合。
ちなみにそのときの主審の名前は牧野明久という。
そのとき、ワタシはテレビの前で泣いた。
【その3】
第49節 横浜FC戦 (11月18日)
完全に力負け。
シーズン終盤の柏戦、そして横浜戦を両方とも落とした。
特にこの試合での城のヘディングシュートはキレイだったなあ。
目の前(右サイド)からのセンタリングがキレイに弧を描いて、ゴール前の城の頭へ飛んでいく。
で、理想的なジャンプのタイミング、理想的な身体の入れ方で神戸DFに競り勝ってゴールを決められた。
チームの順位も1位から3位に落ち、J1優勝が急激に遠のいてJ1J2入れ替え戦の可能性が高まった。
そのとき、ワタシはウイングのメイン自由席で泣いた。。
このページのトップへ戻る
■ホーム観客動員数ベスト3
【その1】 第49節 横浜FC戦 (11月18日) 15,407人 結果 1−2 ●敗戦
【その2】 第48節 柏レイソル戦 (11月11日) 13,776人 結果 3−4 ●敗戦
【その3】 第24節 横浜FC戦 (6月24日) 11,247人 結果 0−0 △引き分け
ホームゲームの合計入場者数は165,834人 1試合平均の入場者数は 6,910人
J2全体での1試合平均入場者数は 6,406人であった。
J1はと見てみると、1試合平均入場者数は 18,292人。 最高が浦和レッズの 45,573人である。
来期はJ1。どれくらいの観客動員があるのだろうか。ぜひ、ウイングスタジアムを満員にしてほしいと思う。
このページのトップへ戻る |